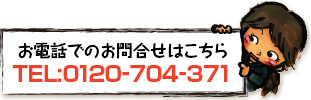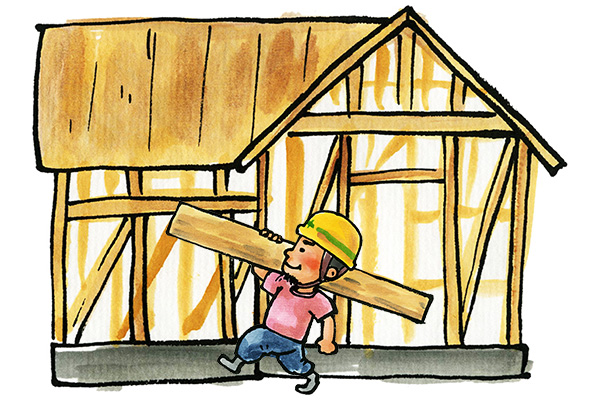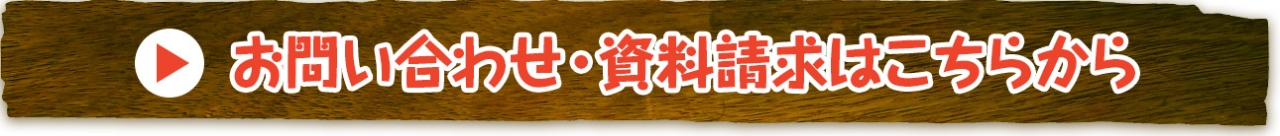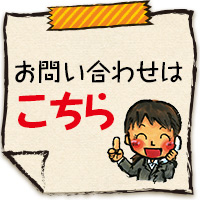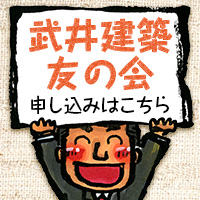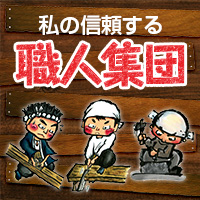三代目棟梁のこだわりと決意
家は買うものではなく建てるもの。お客様と一緒に造っていくものだ
時代の変化
責任の所在
リフォームは大工を中心にしたチームワーク
普段口にする食品だって農家や漁師さんから直接買えると安心です
では、家づくりは元々誰がしてきたのでしょうか?
会社概要

社名 | 有限会社 武井建築 |
|---|---|
| 所在地 | 〒258-0019 神奈川県足柄上郡大井町金子656 TEL:0465–82–8877/FAX:0465–82–1245 |
| 創業 | 昭和25年 |
| 代表者 | 代表取締役社長 武井 勝施 |
| 神奈川県知事許可 | (般 – 27)第81035号 |
| 登録団体名 |
|
アクセス
私の信頼する職人集団
私たちが安心の家をお届けする武井建築のパートナーです

工事総務責任者:武井勝施
藤沢市にあるゼネコン会社へ入社。その後、父親の経営する現在の武井建築へ専務取締役として就任。
平成11年「欠陥住宅撲滅実践会」を自ら主宰。職人たちと現場で汗を流しながらも、厳しい目で現場の管理をしています。お客様との打ち合わせから、現場での作業まで全てに関わります。常にお客様の目線で現場を見ています。他に「欠陥住宅」をなくす運動を執筆活動を通じてお客様に警鐘をならしています。2級建築士でもあります。

材木:小田原木材市場
材木は在来工法の命です。材料選びで家の出来が決まると言ってもいいほど大切です。
特に武井建築さんは、材木一本でも気に入らなければ「持って帰れ!」といわれてしまうので真剣に選んでます。

住宅設備・建材:和以美
快適な生活を送る為に無くてはならないキッチン、ユニットバス、洗面などの水回り商品はどのメーカーでも扱ってますが、自信を持って私がお薦め出来るものだけを武井建築さんに紹介しています。「材質」、「使いやすさ」、「耐久性」この3つの1つでも欠けるものは、大手メーカーであろうとお薦めしません。

基礎:永建興業
何よりも家の中で一番大事な基礎!
どんなに素敵な家でも、その家がのる基礎が頑固でなければ家が傾きます。
頑固な基礎をモットーに、真剣に作っています。武井建築の基礎は強い!

サッシ:大成トーヨー住器
今、窓ガラスはペアガラスが当たり前となりました。
標準仕様にもペアガラスを採用している武井建築さんの家は、暖かい空間を作れることまちがいなし。
サッシのことならどんな要望にも応えます。

電気:西電工
電気工事は家が完成すると天井裏や壁の中に隠れしてしまう配線工事がメインの仕事です。配線ミスにより火災にもつながりますので、見えなくなってしまう配線こそ最大限の気を使っています。
これだけは、全部一人でやらないと気が済みません。
また、テレビやエアコン、照明器具の交換工事もお任せください。

塗装:福田塗装
塗装工事は家のお化粧です。
外も中も私の仕上げ方で家の見栄えが違ってくるので緊張感を持って仕事をしています。
特に内装に使う塗料は、有毒なガスを発生させるような有機系塗料は一切使いません。
武井建築さんは無垢材を使うため「木」本来の呼吸や素材感を殺さないことを常に心がけてます。

水道:内木水道工業
私も親子でやっている水道屋です。
キッチン、お風呂、トイレ、洗面所と快適な水廻りの環境は生活する上で欠かせません。
武井建築さんの工事エリアは全て指定工事店を取得しています。お客様にも安心の一級技能士の水道工事店です。

内装クロス工事:エルインテリア
クロス工事は、内装工事の最後の仕上げです。
私の出来次第で、良くも悪くもなってしまいます。インテリヤの雰囲気も左右してしまう工事ですので、正確丁寧をモットーにしています。特に、壁紙を貼る前の下地処理は時間をかけています。